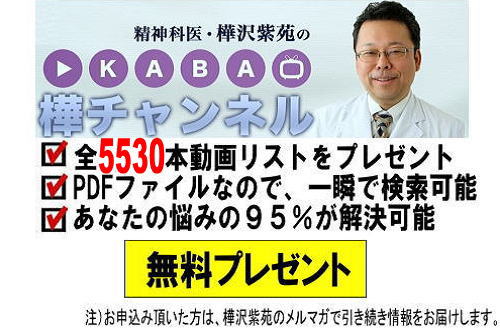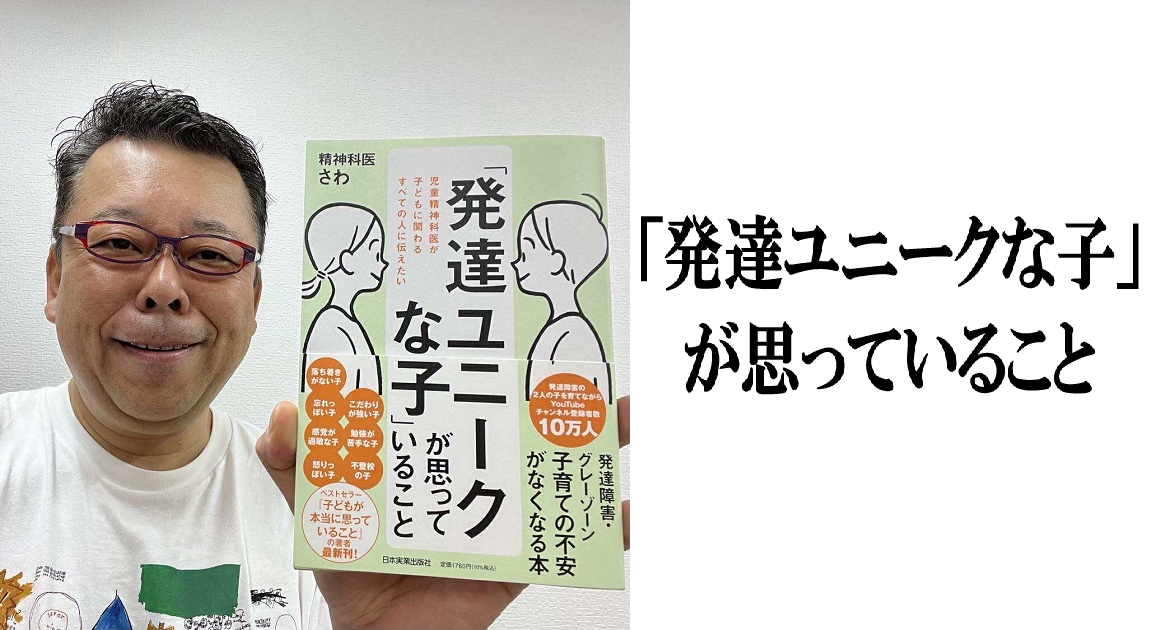「発達障害」への関心は高い。
いろいろなデータがありますが、
日本人の約10%が
「発達障害」の診断基準を満たす、ようです。
さらに「発達障害」の一歩手前の
「グレーゾーン」というのもある。
さらにその手前の
「発達障害かもしれない」と心配する
人たちも多い。
といった言葉の説明を、
いつもYouTubeでしてますが、
説明するほど
「うちの子は発達障害かも」
「自分も発達障害かも」と
不安になる人を増やしている気がして
なりません。
「発達障害」という言葉が、
恐怖感を煽るのでしょう。
なので、日本精神神経学会では、
「発達障害」という呼称はやめて
診断病名としては「神経発達症」に統一しましょう
と決めましたが、
「神経発達症」の呼称は、全く広がりません。
また、「神経発達症」でいいのか、
という問題もあります。
私の本音をズバリ言うと、
「発達障害かどうかは、どーでもいい」
と思います。
重要なのは、診断名ではなく、”困りごと”です。
「不注意が強く、忘れ物が多い」とか
「コミュニケーションに支障を来す」とか。
「発達障害」でも
「グレーゾーン」でも
「かもしれない」でも関係なく、
今、抱える、学校や仕事の「困りごと」
を解消することが重要。
だから、
「発達障害かどうかは、どーでもいい」
のであって、
「今の”困りごと”を一つずつ解消していく」
ことが、精神科の治療やサポートの全て
と言ってもいい。
だから、私のYouTubeでも、
「悩み事」ベースで、みなさんの質問に
お答えしているし、
「診断なんて、どーでもいい」と
いつも言っているのです。
厳密には、
「診断よりも、TO DO(すべきこと)」
が重要、という意味です。
しかし、そう考える人は少ないようで、
書籍やネットの説明を見ても、
発達障害の「症状」の羅列と
「診断」についての話がやたらと多い。
結果として、
「自分の子どもが」あるいは「自分が」
“発達障害かもしれない”と過剰に心配する人が、
たくさん生み出されている。
そんなことを、いつも考えているのですが、
本日発売の
『「発達ユニークな子」が思っていること』
は、「こんな本が欲しかった!」という
一冊でした。
診断名にとらわれることなく、
「すべての人には、それぞれの発達のユニークさ
がある」という視点を、もっと広げていきたい
「困っているなら支援が必要」という考え方が、
もっと社会のなかに広がっていってほしい
私の発達障害に対する考え方と、
ほとんど同じです。
以前より、
発達障害という言葉を使えば使うほど、
「発達障害」と「そうでない人」との分断を進める。
という気がしていました。
本書では、
>すべての人には、それぞれの「発達のユニークさ」
>がある
と明言しています。
誰にでも、「発達のユニークさ」があって、
それによって困ることがあるので、
対応していこう。
精神科医やカウンセラー、教師や親も、
診断ではなく、「困りごと」ベースで、
支援をしていくべき!
全くその通りだと思います!!
なので本書は、
「困りごと」ベースで章立て
されていることが、大きな特徴です。
「落ち着きがない/忘れっぽい」
「感覚が過敏」
「こだわりが強い」
「コミュニケーションが苦手」
「勉強が苦手」
「怒りやすい」
これらに対して、どのように対応するのか。
支援するのか。
「発達障害」か「グレーゾーン」か関係なく
うちの子は「落ち着きがない」と思うのなら、
その章を読めば、現状の深い理解ができて、
対応、対処法、サポートの方法がわかるのです。
そのため、
極めて実践的であり、即効性があると言えます。
「うちの子は、発達障害」
というネガティブなとらえ方から、
「うちの子は、発達がユニーク」
というポジティブな見方に切り替えるたけで、
親も子どもも、ガラッと変わります。
子どもの発達を不安に思う全ての方。
教員、保育士など、子どもと関わる業種の方に
広く読んでいただきたい一冊です。
『「発達ユニークな子」が思っていること』
(精神科医さわ著、日本実業出版社)
アマゾンでの購入は、コメント欄のURLから。

【全動画プレゼント】
あなたの悩みの95%は解決する。
YouTube「樺チャンネル」の全動画5530本のリストをプレゼント中。
今すぐダウンロードしてください。
https://canyon-ex.jp/fx2334/z6j0NW