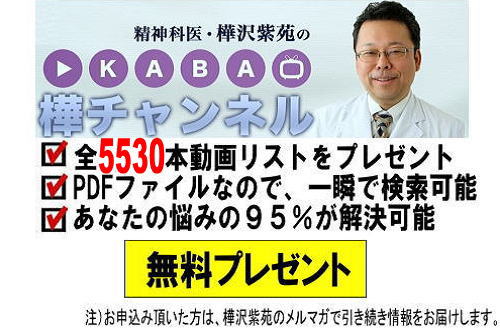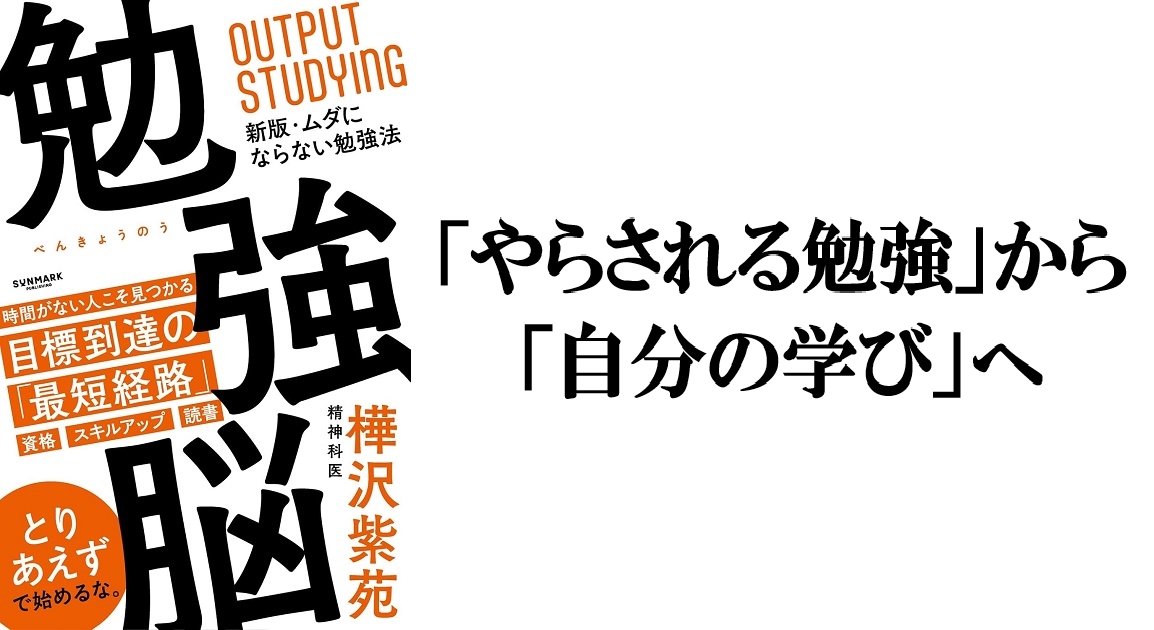「やらされる勉強」から「自分の学び」へ
——英語教師として『勉強脳』を読んで感じたこと——
毎年この時期になると、
「どうやって生徒たちのやる気に火をつけようか」
と頭を悩ませます。
受験が見えてきた中学3年生の教室を見渡すと、
机にかじりついて頑張っている子もいれば、
窓の外をぼんやり眺めながら、
どこかまだ”受験モード”になれない子もいて、
こちらが「さあ、頑張ろう!」と声をかけても、
「はあ……」と力ない返事が返ってくる様子……。
そんなときに出会ったのが、
樺沢紫苑さんの『勉強脳』でした。
正直なところ、最初は書店で手に取りながら
「勉強法の本かな?」くらいの軽い気持ちで読み始めました。
ページをめくっていくうちに、
だんだんと前のめりになって、
「これはただのノウハウ本じゃない」
と気づいている自分がいました。
“勉強って、実は楽しいものなんだよ”
というメッセージが、
脳科学の知見をベースにしっかり伝わってくるんです。
そして、「やらなきゃ」から「やってみたい」へ、
学びに向かう気持ちを切り替えるヒントが、
これでもかというほど詰まっていました。
特に心に残ったのは、
「ちょい難勉強法」と「アウトプット重視」の考え方です。
ちょい難──つまり、ちょっとだけ難しい課題に取り組むことで、
脳がドーパミンを出してワクワクする、という話。
読みながら「あ、これだ!」と手を叩きそうになりました。
これってまさに、
私が授業で意識してきたこととリンクしたんです。
英語の授業では、教科書の文法や表現を使って、
生徒同士でグループワークをよくやっています。
「現在完了形って何?」と最初は苦戦していたあの子も、
友だちと「僕、宿題もうやっちゃった!」
「I’ve already finished my homework!」と
例文を考えている中で、
だんだんと表情が明るくなって、コツをつかんでいく。
その瞬間の「あ、わかった!」という顔を見ていると、
「ちょい難」の力を実感しました。
もうひとつ共感したのが、
「お山の大将勉強法」。
私は授業中、理解が早い子や得意な子に
”スモールティーチャー”をお願いして、
周りの仲間に教えてもらう時間をとっています。
英語の助動詞でつまずいていたときのことです。
ある生徒が「みんな、willとbe going to の違いって知ってる?」
と声をかけて、
ホワイトボードに未来の予定を図で説明してくれたんです。
そのときの生徒の得意げな表情、
教えてもらった側が「あー!そういうことか!」
と手を叩くリアクション──教室に響く「わかった!」
の声を聞いていると、
これこそが、勉強の”喜びの連鎖”だと実感しました。
『勉強脳』のページをめくっていくと、
「インプット3:アウトプット7が理想の比率」
という話も出てきます。
英語こそ、アウトプットが命。
単語や文法をいくら頭に詰め込んでも、
それを”使う”場面がないと、
テストが終わった途端にすぐに忘れてしまいます。
最近は授業でも「今日覚えた表現を使って説明してみて」
「この文法でお互いに会話してみよう」
「習った単語でクイズを出し合って」など、
アウトプットのチャンスを増やしています。
すると、生徒の目が少しずつ変わってくるんです。
授業中に「先生、この言い方で合ってる?」
と積極的に質問する声が増えて、
これは、“わかる”じゃなくて”使える”感覚が
ついてきた証拠だと思います。
もうひとつ、本を読みながら心に刺さったのが、
「才能は存在しない。あるのは適性だけだ」
という言葉です。
正直、私もつい職員室で「あの子はセンスがあるよね」
「頭の回転が早いな」
なんて同僚と話してしまうことがあります。
でも、『勉強脳』のその部分を読んでハッとしました。
「楽しい」と思えるかどうか。
そこが勉強のスタートなんだと。
だったら、私たち教員がすべきことは、
まず「学ぶ楽しさ」を感じさせること。
テストで正解を当てさせるより、
「相手に伝わった!」「友だちに教えられた!」
という経験を積ませること。
それが、自己効力感につながり、
「もうちょっとやってみようかな」
という気持ちを育てるのだと思います。
授業は「わからない子を支える場」だけでなく、
「楽しく学び直す場」「得意を活かす場」にしたいと思っています。
『勉強脳』を読み終えてからは、
知識を一方的に教えるだけでなく、
生徒同士が「こうやったらわかりやすいよ」
「一緒にやってみない?」と教え合ったり
試したりできる時間を意識してつくるようになりました。
勉強が苦手な子も、得意な子も、
それぞれが役割を持って関わる中で、
まさに『勉強脳』が描く学びの姿が、
教室で少しずつ形になってきています。
この本は、生徒より先に、
先生に読んでほしい一冊です。
読むと、自分の授業や声かけ、
そして”学び”への向き合い方が変わります。
私自身、読み終わった翌日から、
教室の空気を少しずつ変えることができました。
「勉強は、やらなきゃいけないものじゃない。
やってみたいと思えたら、もう勝ち。」
このメッセージを、生徒たちと共有できる教室を、
これからも作っていきます。
寄稿者「サッカー小僧」さん
▽ ▽ ▽ ▽
『勉強脳』感想キャンペーン!
残念ながら「最優秀賞」は、「該当者なし」
でしたが、
せっかく感想をお寄せいただいたので、
「最優秀賞・次点」の方の感想文を紹介していきます。
学校の授業で、生徒自身に教える体験をしてもらう。
生徒自身が主体的に考える。
アウトプット型の授業を取り入れてることは、
本当に素晴らしいことと思います。
だったら、私たち教員がすべきことは、
まず「学ぶ楽しさ」を感じさせること。
これは、本当に重要な「気付き」です。
教師や親ができることは、
「勉強しなさい!」と言うことではなく、
「学ぶ楽しさ」を教えることなのです。
『勉強脳』を通じて、
1人でも多くの人が「学ぶ楽しさ」に気付いて欲しい。
また、「学ぶ楽しさ」に気付いた人は、
それを周りの人に伝えていって欲しいのです。
追伸
読んでない人は、そろそろ読んだ方がいい。
あなたの「学び」の常識が、根底から覆る。
↓ ↓ ↓
『勉強脳』(サンマーク出版)

【全動画プレゼント】
あなたの悩みの95%は解決する。
YouTube「樺チャンネル」の全動画5530本のリストをプレゼント中。
今すぐダウンロードしてください。
https://canyon-ex.jp/fx2334/z6j0NW